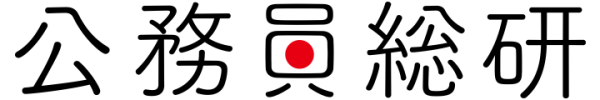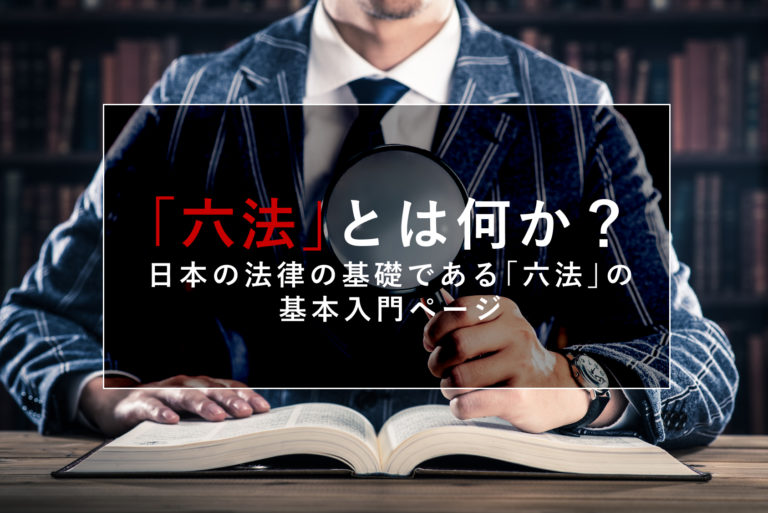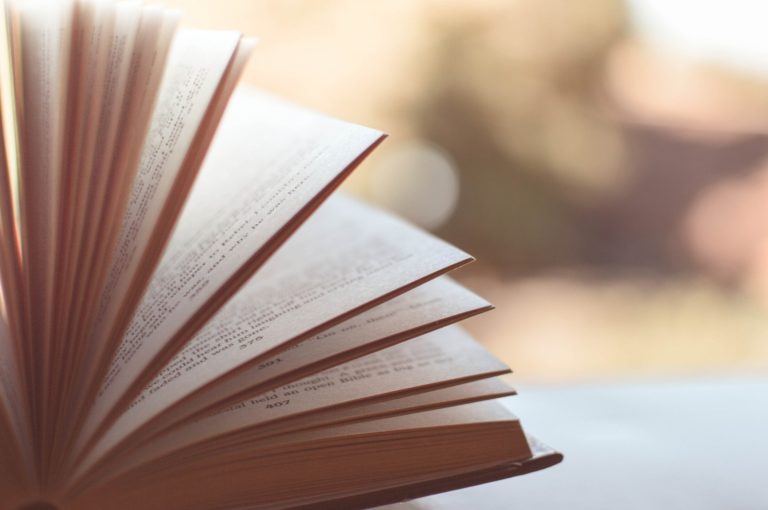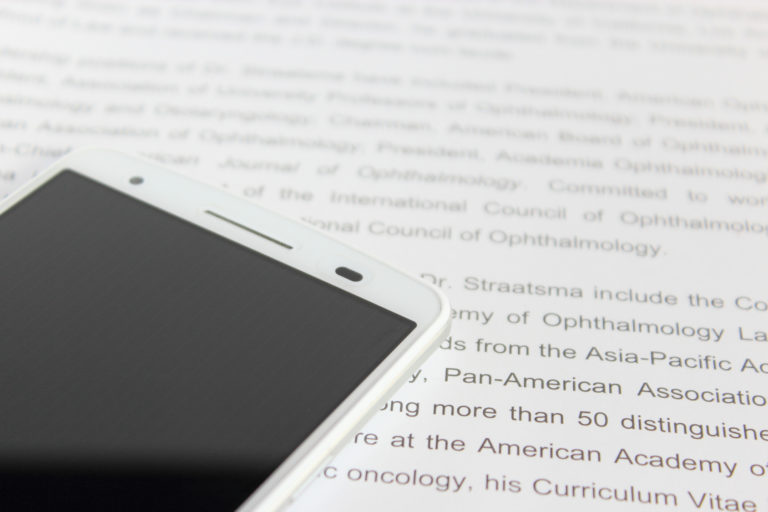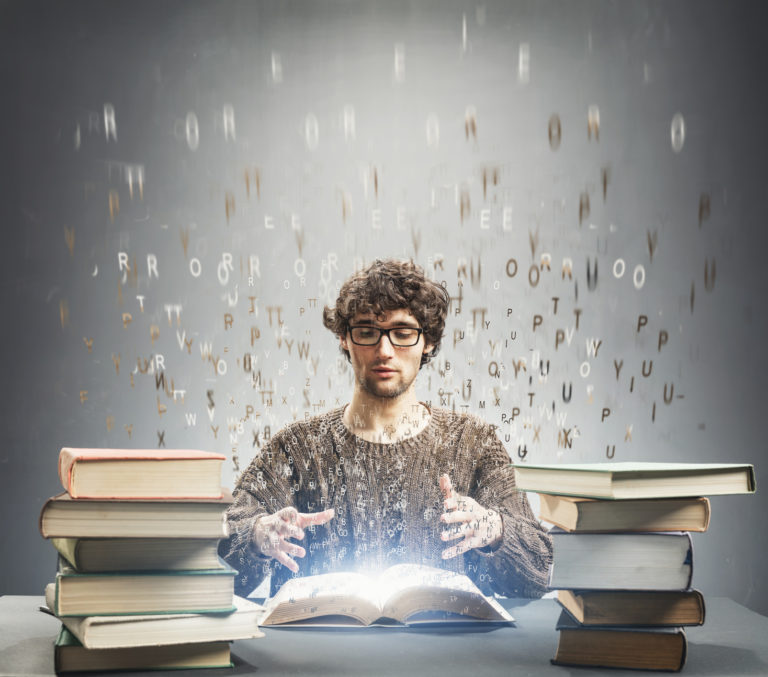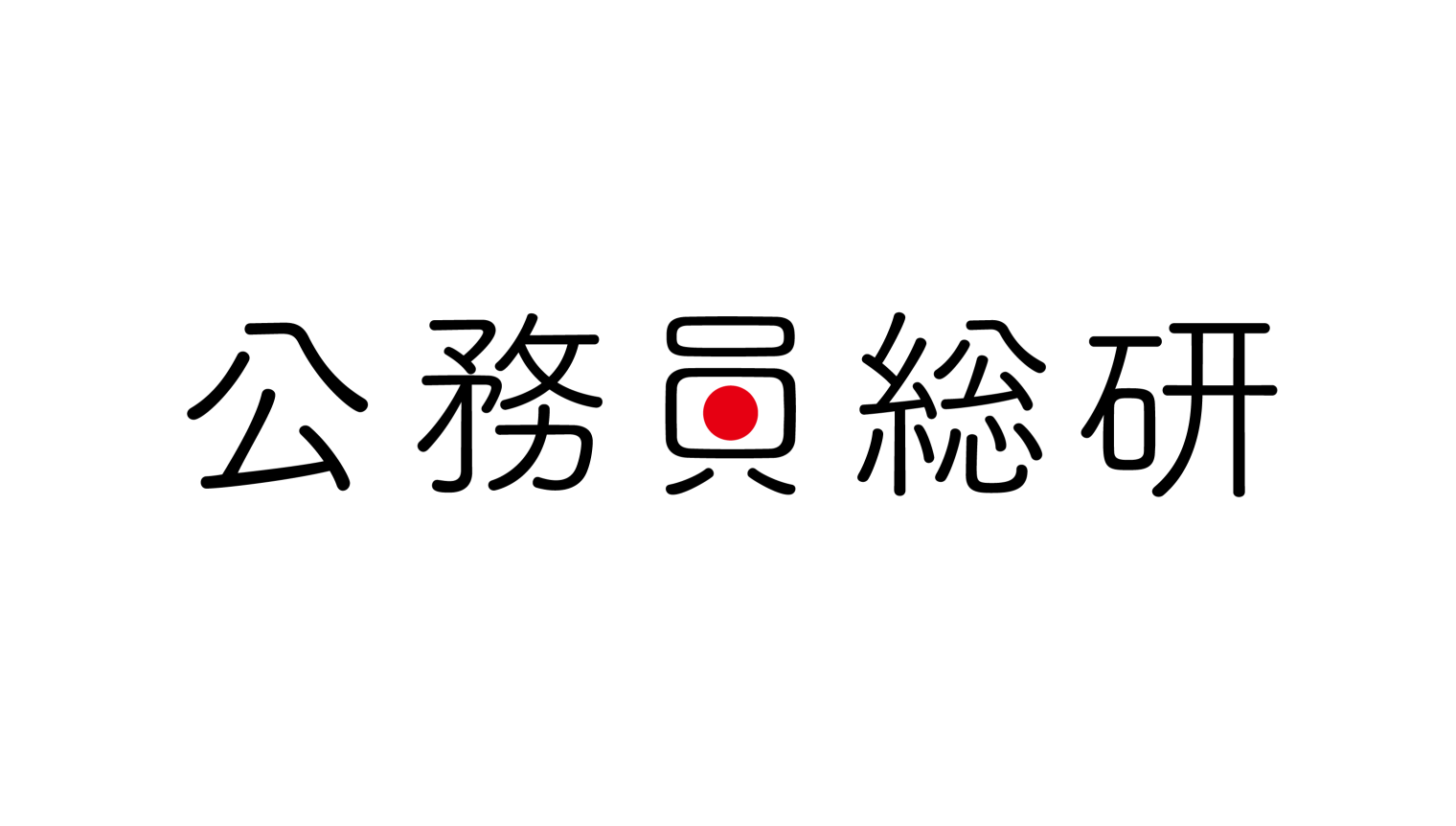全体
日本の政治システム基礎知識に関する記事一覧ページです。
- 2023年2月2日
リモートワークやセキュリティで必須知識「VPN」についての仕組みや導入メリット・デメリットを解説(2023年1月)
昨今はコロナ禍や働き方改革の影響で、テレワークが大きく浸透してきました。テレワークの拡大は民間企業だけでなく、公務員にも波及しています。
テレワークでは、個人情報や重要なデータを取り扱うケースがあります。万が一、情報漏えいが起こると信用問題や社会問題に発展しかねません。そのため、セキュアなテレワーク環境を実現する仕組みであるVPNが必要です。
今回の記事では、公務員にも是非しっておいてほしいVPNの仕組みやメリット・デメリットをまとめました。VPNを賢く利用して、通信セキュリティを向上させましょう。
- 2021年11月2日
有名政治家の家系図について(小泉家・河野家)【有名政治家の家系シリーズ】
政治家の中には、何代にもわたって続く世俗議員一族出身の議員が多く存在します。 その中でも特に有名な、「小泉家」と「河野家」についてご紹介します。
- 2021年10月7日
【有名政治家の家系シリーズ】90・96〜98代首相安倍晋三の家族・兄弟について(2021年10月記事)
親戚に歴代総理大臣や政治家が多く「ロイヤルファミリー」とも囁かれる、前安倍首相の家族や兄弟について、特集します。
- 2020年11月13日
国の特別機関「日本学術会議」って何? - 役割や仕事内容、給料などを徹底解説
「日本学術会議」とは、どんな組織なのでしょうか。
本記事では、「学問の国会」や「研究者の頂点」とも呼ばれる「日本学術会議」の役割や仕事内容について詳しく解説します。
- 2020年7月10日
MMT理論は新世代の金融理論となりえるのか? ― 財政緊縮派の功罪
「MMT理論」についてご存じでしょうか。今、政界やメディアを中心に注目を集めている、金融理論のことです。
本記事では、「MMT理論」とは何か、「MMT理論」は日本の政治経済にどう影響するのかについて、徹底的に解説します。
- 2020年2月27日
感染症発生!その時公務員は?感染症からみる各行政組織の役割
「インフルエンザ」など毎年発生する感染症に加え、「新型コロナウィルス」など新たな感染症が発生した時、さまざまな公務員がその拡大防止に奔走しています。
感染症に関わる公務員を特集します。
- 2020年2月7日
【外務省】ODAってなんだろう?
ニュースなどで「ODA」とよく聞くけれど、意味はわかっていても具体的にどのようなことが行われているのかわからないという方は意外と多いのではないでしょうか。今回はその「ODA」の基本的な意味と、日本での「ODA」の取組の歩みについて解説します。
- 2018年11月16日
どこまで条例で規制して良いのか?-条例制定権の限界
日本には大きく分けて、法律と条例という2段階のルールが存在し、法律とは国会によって決められたルールで、条例は地方議会によって決められたルールです。
今回は、条例は法律との関係性でどのようなとこまで規制できるのか、条例制定権の限界について説明します。
- 2018年11月13日
日本の法律のほとんどは官僚が作っている? 知っておきたい法律の制定過程
日本は三権分立の統治体制になっています。三権分立制度では法律を作るのは立法機関である国会ですが、実務上は国会が主導して法律を作っているわけではありません。
今回は三権分立の理論を踏まえながら、実際には法律はどのような過程を経て制定されるのかについて説明します。
- 2018年6月28日
【道州制とは何か】日本の新たな行政区画の話題について
道州制とは何か?から、アメリカを事例に「州」と「県」の違いなどについて、「地方創生」などをキーワードに基本的な点をまとめました。
道州制は地方に財源と権限を国から移行するために必要な取り組みですが、一部の規制緩和は既に国家戦略特区制度などによって行われています。道州制の是非もふくめて参考ください。