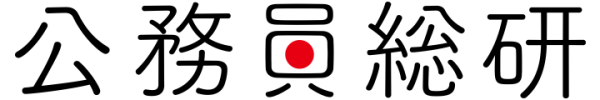東日本大震災– tag –
「東日本大震災」をテーマにした記事の一覧です。
-

【首相官邸発】防災の手引きについて(地震・津波編)
日本の災害と、「首相官邸」が発信する「防災の手引き」 日本では近年、地震・津波、豪雨や大雪、竜巻などの災害が多発しています。2011年の「東日本大震災」は近年で最も大きな被害をもたらしましたが、それ以降も毎年のように豪雨、土砂災害、台風などの... -

【刑務官への感謝状】刑務官の能力が活かされた支援活動
避難者から刑務官への感謝状 東日本大震災で被災した宮城県の石巻での出来事。避難先の小学校に刑務官への感謝状が掲示されたことがありました。そこで支援活動をしていた刑務官に対して避難している方たちが感謝の気持ちを表したものです。 刑務官が被災... -

東日本大震災からの復興を担当する中央官庁「復興庁」の基本情報
はじめに 「復興庁」は、東京都千代田区霞が関にあり、2012年に設置された日本の行政機関です。定員は、207人です。 なお、前身の組織は「東日本大震災復興対策本部」でした。 今回は「復興庁」の公務員を目指す方に押さえておいてほしい基本的な情報と役... -

「敗北感」「葛藤」…隊員があの日目にした光景 東日本大震災当日の体験談
八乙女分署で勤務している、スーパーレスキュー仙台の隊員4名は、当時、それぞれ異なる消防署に勤務されていました。震災当日、実際に体験した貴重なお話をうかがってきました。 岩佐司令補 体験談 私は当時、機動救助隊が配備されているもうひとつの消防... -

消防職員・消防団員の殉職と東日本大震災から得た教訓とは
地方公務員 消防職員の殉職について 現場活動だけでなく訓練で犠牲になることも 今回触れる消防職員とは、各市町村の消防本部に所属する地方公務員です。消防士、消防官などの呼び方がありますが正式名称は「消防吏員」です。なお、本項では後述する消防団... -

東日本大震災における各機関からの支援の手と活動について
全国から集まった警察組織の活動 広域緊急援助隊を被災地へ派遣 警察の仕事というと、犯罪の抑止や交通違反の取り締まり、という面が注目されるかもしれませんが、実は警察の中でも救助活動を行う組織があります。機動隊や、広域緊急援助隊です。日本全国... -

【日本を支える消防官の歩み】痛みを乗り越え、進化した「消防の歴史」
江戸時代から始まった「火消し」の歴史 火事が多かった江戸時代の火消し 「火事と喧嘩は江戸の華」という言葉があります。この名の通り、江戸時代には多くの火災が発生しました。 江戸の町は、長屋などの集合住宅が密集していた事、日本全国でも人口が集中...
1