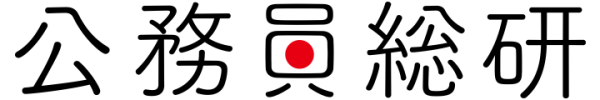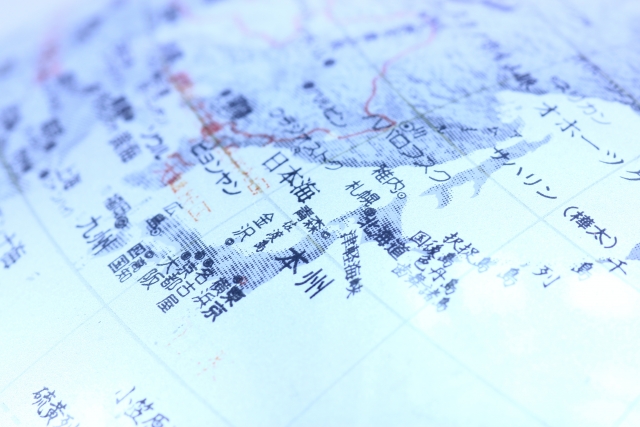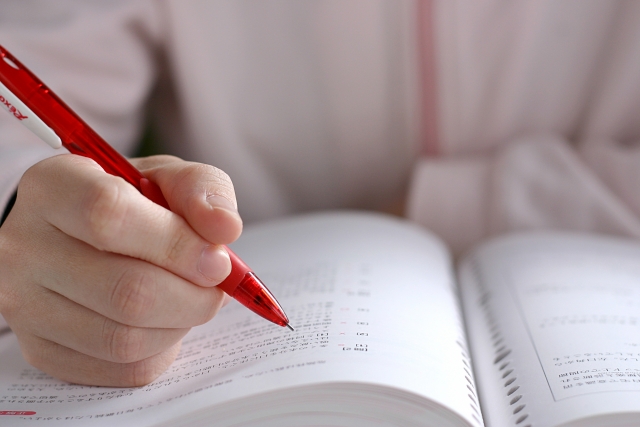日本の政策史– tag –
「日本の政策史」をテーマにした記事の一覧です。主に歴史上の日本で起こった、制度や政策・公共施策などについて解説します。
-

【日本の政策史その9】古代日本の外交「遣隋使・遣唐使」について
日本の政策史シリーズ第9回は、「遣隋使・遣唐使」です。誰もが学校の歴史の授業で学習したことのある「遣隋使」と「遣唐使」について詳しく解説します。日本の古代の外交政策のねらい、そこから日本は何を手に入れたのか。遣隋使、遣唐使として有名なあ... -

【日本の政策史その8】鎌倉幕府とは何なのか?国の権力について考える
日本の政策史シリーズ第8回は「イイクニつくろう鎌倉幕府」の語呂で有名な「鎌倉幕府」についてです。教科書などで誕生年が1192年から1185年に変更されましたが、歴史が変わるのはなぜなのかを説明しながら現代の歴史観について考察していきます。 はじめ... -

【日本の政策史その7】日本の古代政治史上の一大改革「大化の改新」
日本の政策史シリーズ第7回は、「大化の改新」です。ちなみに645年で習ったかもしれませんが、現在は646年という説が有力です。改新の詔についても真実が記されているのかどうかという疑惑ももちあがっています。そんな日本の古代政治史上の一大改革「大... -

【日本の政策史その6】幕末の混乱期に突如あらわれた集団「新選組」とは?
日本の歴史に残る「政策」について取り上げて考察するシリーズです。第6回目は小説、ドラマなど現代で人気の高い「新選組」についてです。「新選組」とはどのような人の集まりなのか?評価が分かれるそのあり方について現代と照らし合わせて考察します。 ... -

【日本の政策史その5】江戸時代の「鎖国」と今の「日本」を考える
日本の歴史に残る「政策」について取り上げて考察するシリーズです。第5回目は江戸時代に行われた対外政策「鎖国」ついてです。「鎖国」は何のために行われたのか、「鎖国」が現代の日本に及ぼした影響はどのようなものなのか、現代と照らし合わせて考察... -

【日本の政策史その4】聖徳太子の「十七条憲法」について
日本の歴史に残る「政策」について取り上げて考察するシリーズです。第4回目は聖徳太子が制定した「十七条憲法」についてです。役人が守るべき規範として「十七条憲法」が制定された背景やその目的・内容について考察していきます。 はじめに 1947年5月3... -

【日本の政策史その3】豊臣秀吉の「刀狩り」は、身分制度政策?
日本の歴史に残る「政策」について取り上げて考察するシリーズです。第3回目は、豊臣秀吉が天下統一のために行った「刀狩り」についてです。なぜ刀狩りが必要だったのか?また刀狩りが現代の日本にもたらしている影響についてさらには、アメリカと比較し... -

【日本の政策史その2】廃藩置県とは何なのか?「日本人」が生まれた瞬間
日本の歴史に残る「政策」について取り上げて考察するシリーズです。第2回目は明治維新最大の改革とも言われている「廃藩置県」についてです。廃藩置県を通して、現代の日本に必要な政治改革はどのようなものか考察していきます。 はじめに 鎖国を続けて... -

【日本の政策史その1】イヌは殺してはダメ?「生類憐みの令」
日本の歴史に残る「政策」について取り上げて考察するシリーズです。第1回目は、江戸時代の江戸幕府、5代将軍の徳川綱吉による「生類憐れみの令」についてです。徳川綱吉ってどんな人?から「生類憐みの令」とはについて解説します。 戦乱を終えが江戸時...
1