「民法」により解釈される「相続」とは
まず、誰でも一度は聞いたことがある「遺言」ですが、これは、民法に従っていなければ、その効力を発揮できません。遺言と認められるには、決まった形式があります。このような表現方法をすると、誤解を招くかもしれませんが、実際に遺言に不備があった場合は、その遺言通りに執行されることはありません。
通常は、こういった事態を避けるために、公証役場で公証人の立会いのもと、不備のない遺言書の作成を行います。また遺言書は何度でも書き換えることができますので、「一度かいてしまったら、書き直しができないかも」といった心配はする必要がありません。
ただし、書き直した遺言書は廃棄することなく、すべてを残しておく必要があるため、場合によってはその量が膨大になる可能性があります。当然のことながら、書き直したその順番も重要ですから、やはりしっかりとした公証役場で遺言書を作成する方が望ましいといえます。
遺言には、民法で認められた、3つの方法があります。
まず1つ目は、「自筆証書遺言」といわれるものです。これは、「遺言の内容をすべて、遺言者が手書きで作成すこと」となっており、最近はやりのスマホ等での録音は、無効となっています。またよほどのことがない限り、代筆やパソコンでの作成は、無効という取り扱いになりますので、この点には注意が必要です。
2つ目は、「秘密証書遺言」といわれるものです。これは、被相続人が作成した遺言書を、封筒等に入れて密封しその封書を公証役場へ提出し、公証人と承認の立会いのもと、遺言書の存在を明らかにしておくものです。この場合の立会人は、税理士やその補助者が立ち会うことができます。多くの場合、その後の相続税の申告を視野に入れて、事前に、将来申告をお願いするであろう税理士の方に、依頼することが多いようです。
最後に3つ目は、「公正証書遺言」お言われているものです。これは、公証役場で手数料を払い、公証人に遺言書を作成してもらうものです。そもそも、遺言書というものがどういったものかわからないといった人には、この方法が「一番確実な方法」ということができます。
そして上記のような方法で作成した遺言書を執行するためには、「遺言執行者」と呼ばれる人を選択をて置くことが、無難だといえます。遺言執行者については、絶対に選出しておかなければならないといったものではありません。しかしももともと相続については、争いの起こりやすいものです。自分がなくなってから、まさかそのような問題が起こっているとは、思いもよらないことですし、当の本人にはわからないことです。遺言内容を滞りなく執行するために、自分とは利害関係がない、つまり赤の他人の専門家に依頼するのがべすとだといえます。
このように、民法で規定されている相続の内容は、大まかにいえばこのような形になります。
では、相続税という税法が定める相続とはどのような規定があるのでしょうか。
相続税法における「相続」の規定とは?
相続税における「相続」とは、あくまでも「税金」の定義になります。
税務大学校で使用する教科書には、「相続税は、死亡した人(被相続人)の財産を相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した配偶者や子など(相続人等)に対して、その取得した財産の価額を基に課される租税である。」(「http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/souzoku/pdf/01.pdf#page=1」抜粋)
という説明がされています。この一文からも判断できるように、あくまでも「税金」という定義になるのです。
それと同時に、相続税を徴収することにより、所得税を補完する、といった意味合いもあります。それがどういうことかといえば、「被相続人が生前において受けた社会及び経済上の要請に基づく税制上の特典、その他による負債の軽減などにより蓄積した財産を相続開始の時点で清算する、いわば所得税を補完する機能である」といった定義も明言されています。
「所得税を補完する相続税」ときくと、少し意味が分かりにくいかもしれませんが、日本の税法上、種類の違う税金が同じ一つの課税対象に対して課せられるといったことはありません。
このような理由からもわかるように、相続税が課せられているのであれば、それは所得税の課税対象ではない、といった解釈になります。
ただしこの逆で、相続税が課せられなかった場合は、所得税の課税対象となる可能性があるということもできます。単純に「相続税の対象ではなかった。」と安心することはできない、ということになるのです。
また、相続税を課する理由にはほかにもあります。それは一カ所に財産を集中させない、といった意味合いがあります。相続したものとしなかったものとで、不平等が生じるようなことがあるのであれば、それは税金として徴収することにより、解消することができるといった意味もあります。
確かに一つの財産を相続できなかったために、所得格差ができるのであれば、それは財産がもらえなかった側からすれば、少々納得しがたいものがある、ということができます。ですから「平等性を保つ」といった意味でも相続税は、徴収すべきだという国の考えになっています。
これらを総合的に見てもわかるように、相続とは一筋縄ではいかないのが理解できるのではないでしょうか。
では実際に財産を相続する際に、どういった相続順位でどういったことが考えられるのか、という点に次は触れていきます。
気になる相続順位とは?そしてどのようなことが考えられるのか?
どういった順序で相続財産を継承するのか、気になるその順位について少し触れていきます。
日本で定められている相続税法上の、相続順位は以下の通りです。
1.配偶者
2.子(代襲相続人(孫、曾孫など)を含む。)
3.直系尊属(父母、祖父母など)
4. 兄弟姉妹(代襲相続人(おい、めい)を含む。)
このように定義はされているのですが実際にそれを証明するものが必要になってきます。それが役所で発行する『戸籍謄本』になるというわけです。
実際に子の戸籍謄本で何を調べるかといえば、本当に被相続人との相続人として権利があるのかどうかという点です。あと把握していない子がいないか、ということも確認します。把握できていない子、つまりは『隠し子』ということになります。隠し子であっても被相続人が認知をしていれば、相続の権利があるため、そこは見逃せないポイントとなります。
そして次に見逃せないポイントは、財産といえど必ずしもプラスの財産だけではない、ということです。いわゆる負の財産、具体的に言えば借入金などの返済しなければいけないもの、返さなくてはいけないもの、支払わなければいけないもの、これらがこの「負の財産」に当たります。
相続とはうまくできており、プラスの財産を相続するのであれば、マイナスの財産も相続しなければなりません。もちろん税金を計算する際には、それらを差し引きして、プラスが出たら、課税の対象となる金額かどうかを判断します。そうでなければその時の相続税の申告は必要ないということになります。
相続は『争続』ともいわれるくらい、もめ事が多いのが事実です。身内とはいえ、お金や財産となれば目の色が変わる人もいます。そういったもめ事へ発展しないためにも、相続をよく理解して準備を進めておく必要があります。
最近の相続の問題点が、今の日本の現状を表しています
どういった事情が、最近の日本の問題と共通しているのかと考えれば、相続の場合は「空き家問題」が、それに該当します。
昨今の日本における少子化と、核家族化により祖父や祖母が住んでいた家に住むことも、処分することもできずに、さらには代々発生する相続の際に登記の変更を行わなかったため、結果的に誰が持ち主なのかわからなくなっているといった場合もあります。
持ち主が特定できる場合は、固定資産税等の問題もあるので、役所から連絡くる場合があります。このような場合、その空き家が近隣住民に損害を与えていたりする場合があるので、速やかに対処すべきであるということができます。
このように、最近の日本の問題点が、如実に表れるのがこの「相続」と言われるものなのです。
相続は一般常識や社会通念上で判断されるものです
相続を的確に判断したり、申告したりするには、社会的通念上という一般常識の感覚が必要になってきます。しかし逆に考えれば、ごく普通の解釈ができるものだということができます。
税金などの細かい数字の計算はさておき、「相続とは」といった概要を考える際には、専門的な知識がなくてもある程度の予測ができるものになります。残された人が困らないような生活を送るための法律である、と、捉えることができれば意外ともっと奥深く知りたくなるかもしれません。
プラスの財産だけを相続することはできない、当然マイナスの財産があればそれも相続する、これだけを聞いただけでも、非常に平等な判断をするものだ、ということが分かるのではないでしょうか?
実際に相続の手続きをするには、それなりに謄本などの書類を集めなければいけないので、そういった意味での時間と手間はかかりますが、やってみるだけの価値があるものだ、と結果的に言うことができるでしょう。
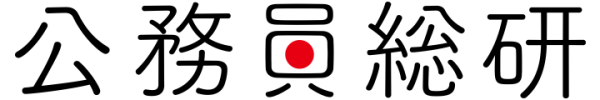









コメント