はじめに
「原子力規制委員会」は、東京都港区六本木にあり、2012年に設置された日本の行政機関であり、環境省の外局です。定員は、968人です。
なお、前身の組織は「原子力安全委員会」「原子力安全・保安院」「文部科学省」「国土交通省」でした。
今回は「原子力規制庁」の公務員を目指す方に押さえておいてほしい基本的な情報と役割について解説します。
「原子力規制庁」について
「原子力規制庁」は、東京都港区六本木に置かれた環境省の外局で、長は、原子力規制庁長官です。
「原子力規制庁」は、2011年3月11日に発生した東京電力福島原子力発電所事故の教訓に学び、このような事故を二度と起こさないよう、原子力規制組織に対する国内外の信頼回復を図り、国民の安全を最優先に原子力の安全管理を立て直すために設置された「原子力規制委員会」の事務局です。
なお、「原子力規制庁」が窓口になっている「原子力規制委員会」は、原子力にかかわる者として高い倫理観を持ち、常に世界最高水準の安全を目指ことを自覚し、たゆまず努力することを理念として活動しています。
「原子力規制庁」の役割について
「原子力規制庁」の役割は、原子力に対する確かな規制によって人と環境を守ることです。
また、「原子力規制庁」は、「原子力規制委員会」の事務局としての役割を担っています。
このような「原子力規制庁」の主な業務は、原子力安全規制、核セキュリティー、核不拡散の保障措置、放射線モニタリングなどです。
なお、「原子力規制庁」が事務局となる「原子力規制委員会」は、大きく5つの原則に基づいて職務を遂行しています。
「原子力規制委員会」の原則
(1)何ものにもとらわれず、科学的・技術的な見地から、独立して意思決定を行う。
(2)形式主義を排し、現場を重視する姿勢を貫き、真に実効ある規制を追求する。
(3)意思決定のプロセスを含め、規制にかかわる情報の開示を徹底する。また、国内外の多様な意見に耳を傾け、孤立と独善を戒める。
(4)常に最新の知見に学び、自らを磨くことに努め、倫理観、使命感、誇りを持って職務を遂行する。
(5)いかなる事態にも、組織的かつ即座に対応する。また、そのための体制を平時から整える。
「原子力規制庁」の組織構成について
「原子力規制庁」の組織構成は、「原子力規制委員会」の事務局として「原子力規制庁長官」「原子力規制庁次長」と、「長官官房」「原子力規制部」によって成り立っています。
事務局のほか、「施設等機関」である「原子力安全人材育成センター」と「審議会等(原子炉安全専門審査会など)」があります。
「原子力規制庁」の年間予算(一般会計)は、約56億4千万円
「原子力規制庁」が事務局として運営する「原子力規制委員会」の平成30年度の予算は、約56億4千万円でした。
その主な内訳項目は、大きく8つに分かれています。
(1)原子力規制人事育成事業費
(2)試験研究炉等の原子力の安全規制に必要な経費
(3)試験研究炉等の核セキュリティ対策に必要な経費
(4)放射性同位元素使用施設等の規制に必要な経費
(5)放射線安全規制研究戦略的推進事業費
(6)保障措置の実施に必要な経費
(7)放射線測定に必要な経費
(8)放射能調査研究に必要な経費
これらの経費の中で、(6)保障措置の実施に必要な経費は31億9千円で、一般会計の半分以上を占めています。
内訳についてはこちらの予算概算要求の概要をご参考ください。
http://www.nsr.go.jp/data/000214733.pdf
まとめ
いかがでしたか?
「原子力規制庁」は、「環境省」の外局として、また、「原子力規制委員会」の事務局として高い倫理観を持って原子力を規制し、常に世界最高水準の安全を目指して業務を行っています。
ちなみに、「原子力規制庁」の英語名称は「Nuclear Regulation Authority」で、略称は「NRA」です。
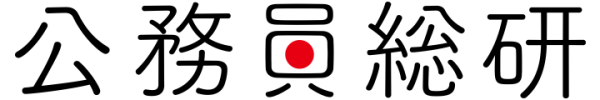










コメント