「地方公務員」と「国家公務員」の「福祉職」とは?
「福祉系公務員」とも呼ばれる、「公務員」の「福祉職」には、「地方公務員」として勤務する職種と、「国家公務員」として勤務する職種があります。
「地方公務員」には「地方公務員上級福祉職」や、自治体ごとに「福祉職」としての採用区分があり、主に地域の人々の福祉に関わる仕事に従事しています。自治体の方針や状況などによって採用人数は大きく差がありますので、各自治体の確認が必要です。
なお、ここでいう「地方公務員上級福祉職」の「上級」とは「地方自治体」の中でも「都道府県」や「政令指定都市」に所属していることを指します。「道府県」や「政令市」には採用区分にも「上級(大卒程度)」「中級(短大卒程度)」「初級(高卒程度)」という分け方がありますが、ここでの「上級」は「都道府県」と「政令指定都市」という意味合いです。
「福祉職」として、大卒・短大卒・高卒のどの最終学歴者を採用対象とするのかは、自治体や職種によっても異なります。志望する自治体の職員募集要項で確認してみてください。
一方で、「国家公務員」には「福祉職」という区分はなく、「福祉職」関連の職種としては、「国家公務員総合職」の「人間科学区分」や、「裁判所総合職(家裁調査官補)」「法務省専門職員(人間科学)」が該当します。「国家公務員総合職」の「人間科学区分」で採用されると、勤務先は厚生労働省や、法務省が多く、「行政区分」などと比べると採用先は限定され、より専門知識を活かした配属先が望めるとも言えます。
ただし「人間科学区分」は「福祉職」に加えて「心理職」や「教育職」などを志望する人も受験するため、「福祉職」としての採用人数は狭き門となっているようです。
「地方公務員」の「福祉職」について
それでは、まずは、「地方公務員」として働く「福祉職」にはどのような職種があるのかご紹介します。
「福祉職」や「社会福祉区分」での職員採用試験があるのは、都道府県や政令指定都市、そして東京都の特別区であり、「地方公務員上級試験」の一部として行われるのが一般的です。
政令市以外でも、「福祉職」の採用を行う自治体もあるようですが、全ての自治体に「福祉職」の採用区分があるわけではありませんので、受験の際には注意しましょう。
【地方公務員上級福祉職】都道府県の場合
地方公務員上級(地上)の「福祉職」として採用された場合、どのような仕事に就くのか、「長野県」の例をご紹介します。
長野県の場合、平成29年時点で、73名の「福祉職」の職員が在籍しており、様々な部署、施設で活躍しています。
地方公務員上級の「福祉職」の勤務先は、自治体により名称など異なる点もありますが、仕事内容では似ているところもあります。長野県以外を志望する場合でも、部分的に参考にしてみてください。
参考:長野県職員採用案内~社会福祉職~
https://www.pref.nagano.lg.jp/jinjii/kensei/soshiki/soshiki/boshu/pamphlet/documents/syahuku.pdf
「県庁職員」として働く「福祉職」の仕事内容
長野県では、「福祉職」として県庁で勤務する場合、「県民文化部」や「健康福祉部」に配属されているようです。
「県民文化部」では「子ども・家庭課」に所属し、子どもへの虐待や、DVの防止に関する業務、保育に関する業務、ひとり親家庭などの福祉を必要とする家庭に関する業務等に携わります。
「健康福祉部」では「地域福祉課」や「介護支援課」「障がい者支援課」で「福祉職」の方々が活躍しているようです。
それぞれの仕事内容について「地域福祉課」では、「福祉人材の確保や養成」「生活困窮者の対策」「社会福祉施設の指導や監査」などが主な業務です。「介護支援課」では、「介護保険の運営支援」や「介護保険事業者の指定や指導」「老人福祉施設の整備」などが主な業務です。そして「障がい者支援課」では「障がい者差別解消」や「障がい者や障がい児施設の整備」「障がい者スポーツの振興」などを業務としています。
長野県以外でも、県庁職員として勤務する「福祉職」は、福祉制度の立案や運営、管轄内の福祉施設の指導や監査業務などを担当することが多いようです。
「児童相談所」で働く「福祉職」の仕事内容
長野県では「福祉職」として採用された職員の多くが、「児童相談所」で勤務しています。「児童相談所」は県内5カ所にあり、子どもの福祉についての「相談業務」や、子どもや家庭の「調査業務」や保護対象となるかなどの「判定業務」を担当します。
実際に子どもの状況によって何らか指導が必要になった場合には、子どもやその保護者に必要な「指導業務」や、「一時保護業務」を担当することがあります。また子どもを守るためには、市町村との連携も欠かせませんので、市町村への必要な「援助業務」を行うこともあるようです。
「児童相談所広域支援センター」で働く「福祉職」の仕事内容
長野県では「児童相談所広域支援センター」といって、各児童相談所だけでは対応が困難な案件や、より専門的な知識が必要な案件について支援したり集約したりする施設があります。
このように自治体独自の施設で、地域の福祉業務のまとめ役として、より広域的で専門的な仕事を担当する「福祉職」の方もいます。
「児童自立支援施設」で働く「福祉職」の仕事内容
長野県では、「児童自立支援施設」で勤務する「福祉職」の職員がいます。「児童自立支援施設」や「児童養護施設」については全国の都道府県に設置されていますので、多くの自治体で「福祉職」で採用された職員の勤務地になっています。
「児童自立支援施設」での「福祉職」の仕事内容は、児童への「生活指導業務」や「生活支援業務」をはじめとした、児童の生活のあらゆる面に関わる業務を担当します。勤務形態については、24時間体制で施設を管理するため、夜勤を含むシフト制が一般的なようです。
「女性相談センター」で働く「福祉職」の仕事内容
長野県では「女性相談センター」で働く「福祉職」の方もいます。「女性相談センター」は、女性が抱える様々な問題への相談業務、配偶者暴力相談支援センターとしての、DVに関する相談業務などを担当します。
「女性相談センター」は「厚生労働省」が、「売春防止法」と「配偶者暴力防止法」に基づいて、全国の都道府県に1つずつ設置する「婦人相談所」の一つです。全国の「婦人相談所」は「女性相談所」や「男女共同参画相談センター」など、都道府県ごとに名称が異なりますが、売春の恐れのある女性の保護・厚生を目指す「婦人相談所」としての機能と、配偶者暴力から女性を保護する「配偶者暴力相談支援センター」としての機能を併せ持っています。
「女性相談センター」については国が設置する機関ではありますが、長野県のように県職員もスタッフとして加わっている場合もあります。
「保健福祉事務所」で働く「福祉職」の仕事内容
長野県では、県内10ヶ所に設置している「保健福祉事務所」の「福祉課」に、多くの「福祉職」の方が勤務しています。「保健福祉事務所福祉課」では、「高齢者福祉業務」や「児童福祉業務」「各種手当に関する業務」「障がい者・障がい児福祉業務」「生活保護業務」「恩給業務」など、地域のあらゆる福祉業務を扱います。
「保健福祉事務所」は「保健センター」や「健康福祉センター」などの名称で全国に設置されており、それぞれ「福祉職」の方が主に相談業務などで活躍しています。長野県に限らず、「福祉職」として採用された地方公務員として、最も多い勤務先の一つと言えます。
「福祉大学校」で働く「福祉職」の仕事内容
長野県では「長野福祉大学校」で働く「福祉職」の職員がいます。「福祉大学校」では、「保育学科」や「介護福祉学科」での「教授業務」を担当し、未来の福祉人材の教育・育成に取り組みます。
現在、全国の都道府県が設置する「福祉大学校」や「保育大学校」は減少傾向にあり、「大学校」で教授として勤務する「福祉職」の枠も減ってきていると思われます。長野県のほかには、栃木県にも「衛生福祉大学校」が設置されていますが、大学校での「教授業務」に携われるのは一部自治体の「福祉職」に限られるようです。
「精神保健福祉センター」で働く「福祉職」の仕事内容
長野県では、「精神保健福祉センター」にも「福祉職」を配属しています。「精神保健福祉センター」は、東京都に3ヶ所、そのほかの道府県と政令指定都市に1ヶ所ずつ設置されている機関です。「こころの健康センター」などの名称で設置している自治体もあります。
「精神保健福祉センター」での「福祉職」の業務内容は、精神保健や精神障がい者福祉についての「知識普及業務」「調査研究業務」のほか「相談・指導業務」などを担当します。
「総合リハビリテーションセンター」で働く「福祉職」の仕事内容
長野県では「長野県立総合リハビリテーションセンター」にも「福祉職」の職員を配置しています。「リハビリテーションセンター」での「福祉職」の業務内容は、
「センター利用者への生活支援業務や相談業務」、「身体障害者手帳や補装具の支給業務」「自立支援医療等の判定業務や相談業務」などです。
長野県のように、自治体が公立の「リハビリテーションセンター」を設立・運営している場合は、「福祉職」として採用された県の職員が勤務する場合があります。
【地方公務員上級福祉職】政令指定都市の場合
地方公務員上級(地上)の「社会福祉職」として採用された場合に、どのような配属先・仕事内容があるのか、「神奈川県横浜市」の例をご紹介します。
横浜市では、現在約1,500名の社会福祉職の職員が勤務しており、基礎自治体としては全国で最も多い370万人という市民の福祉を支えているようです。約1,500名の福祉職職員のうち、約200名が「責任職」に就いており、「社会福祉職」であっても管理職に昇任される可能性が十分にあり得ると言えます。
参考:横浜市採用案内ホームページ「社会福祉職 採用案内」
http://www.city.yokohama.lg.jp/jinji/panf/pdf/h29/h29-syafuku-panf-all.pdf
「区役所(福祉保健センター)」で働く「社会福祉職」の仕事内容
横浜市では、全体の「社会福祉職」の3分2に相当するおよそ1,000名の職員が、市内の18ヶ所の区役所に配属されているようです。各区役所では、主に「福祉保健課」「高齢・障害支援課」「こども家庭支援課」「生活支援課」での業務を担当しています。
具体的な仕事内容をご紹介すると、「福祉保健課」では区の福祉政策としての「地域保健福祉計画」の策定や、社会福祉協議会との連携など、区の福祉の地域づくりを計画・担当しています。
「高齢・障害支援課」では、高齢者や障害者から寄せられる福祉保健サービスについての個別相談業務や、高齢者や障害者としての権利擁護、虐待防止などのために、必要な地域機関との連携業務などを担当しています。
「こども家庭支援課」では、子どもの養育に関することや、障害児への福祉支援サービスについての相談業務や、支援業務を行います。学校や児童相談所との連携が必要な業務もあり、きめ細やかな対応が求められます。
「生活支援課」では、生活困窮者への自立支援に向けた相談業務や、生活保護の相談・認定業務を通した支援を担当しています。
それぞれの部署で、窓口や電話での相談を受け、必要があれば訪問を行う職員は「ケースワーカー」とも呼ばれます。「横浜市」に限らず、「ケースワーカー」として採用される「政令指定都市」などの「社会福祉職」の方は大勢いらっしゃいます。
どの自治体に勤務するにしても、地域の福祉を担当する「社会福祉職」は、相談者本人とのコミュニケーションが重要なのはもちろん、関係機関との連絡や調整も重要な仕事と言えるでしょう。
「市役所」で働く「社会福祉職」の仕事内容
「横浜市役所」で働く「社会福祉職」の職員は、主に「こども青少年局」や「健康福祉局」に配属されています。どちらも横浜市の福祉政策や福祉制度の中心的存在とも言える部局であり、政策立案や運営、予算管理などを担当します。
横浜市役所の「こども青少年局」には「こども福祉保健部・こども家庭課」や「障害児福祉保健課」があり、障害児に関する事業や、DV防止・虐待防止等の事業を企画・調整・推進しているようです。また、市内の児童相談所や児童養護施設を管轄しており、運営支援なども行います。
横浜市役所の「健康福祉局」には「生活福祉部生活支援課」や「障害福祉部障害支援課」「高齢健康福祉部高齢在宅支援課」があり、高齢者、障害者、生活支援者など、主に成人の福祉事業について、企画・運営・推進・予算管理等を担当し、その業務は多岐にわたるようです。市内の障害者支援施設の運営支援についても担当します。
【地方公務員一般職(中級・初級)】「介護福祉士」の仕事内容
公立病院や、公立の高齢者福祉施設、障害者支援施設等で勤務する「介護福祉士」も「福祉系公務員」です。地方公務員の「介護福祉士」として採用されるには、「介護福祉士」の資格が必要だという場合が多いようです。有資格者であれば、高卒程度から受験できることがあります。また、経験者のみ採用という場合もあります。
「地方公務員」の「介護福祉士」は市町村での募集が一般的で、給与や待遇は市町村職員の「一般職」と同じくらいの水準として扱われることが多いようです。採用の段階で勤務先が固定されていることもあり、任期付という場合もあります。同じ自治体の採用であっても条件が異なる場合もありますので、試験ごとに確認することが必要です。
「地方上級」の「福祉職」のように定期採用というケースは少なく、毎年は採用を行わないという自治体や、施設ごとの欠員による募集をしている自治体が多いようです。「地方公務員」の「介護福祉士」を目指す場合には、一年を通して近隣の自治体で募集が無いか、常に注意しておくことで採用されるチャンスが広がるでしょう。
【まとめ】ケースワーカーが中心の「福祉系地方公務員」
「福祉職」や「社会福祉区分」として採用された「地方公務員」の仕事内容について、長野県や横浜市を例にご紹介しました。長野県や横浜市特有の仕事内容もありましたが、多くはどの自治体の「福祉職」にも共通する仕事内容です。
「福祉職」の様々な勤務先や仕事内容をご紹介しましたが、「福祉系公務員」の多くが各施設において「ケースワーカー」として活躍しています。
そもそも「ケースワーカー」とは「相談員」の事を指し、自治体ごとに設置されている福祉事務所などの公的な福祉施設に勤務し、身体面や精神面などで社会的な生活に困難を感じる人々の相談業務を担います。
公務員の「福祉職」になると、「ケースワーカー」として現場での相談業務に従事したり、福祉政策立案や、福祉制度運営に携わり「ケースワーカー」の職場環境を整えたりするなど、「ケースワーカー」の業務を中心に様々な業務を担当することになるようです。
「福祉職」には「ケースワーカー」としての知識が必要となる勤務先が多く、「福祉職」として採用されるための受験要件として「社会福祉士」や「社会福祉主事」などの資格が必要な自治体もあります。資格取得のためには専門科目を学べる大学や専門学校を卒業する、通信講座を受講するなどの方法があります。
自治体勤務の「福祉職」の一つである「ケースワーカー」が具体的にはどのようなタイムスケジュールで勤務しているのかを知りたい方は、下記のページもご覧ください。
「国家公務員」の福祉職について
「国家公務員」には「福祉職」や「社会福祉職区分」と呼ばれる職区分は無く、「人間科学区分」での採用となり「人間科学職」などと呼ばれます。
「国家公務員」の「人間科学職」には「国家公務員総合職」と「国家公務員専門職」があります。
「国家公務員」の「人間科学職」の中でも、「福祉」を担当する分野にはどのような職種があるのかご紹介します。
【国家公務員総合職】の「福祉職」について
「国家公務員総合職」の「人間科学区分」で合格した場合に、「福祉分野」で採用される可能性があるのは、「厚生労働省」や「文部科学省」「法務省」「警察庁」などです。
近年の「国家公務員総合職」の専門試験は、3部構成になっており、まず1部で「人間科学」分野の基礎知識を問われます。ここでは心理、福祉、教育、社会の分野から大学卒業レベルの一般教養を問われます。
2部、3部では「心理系」と「教育・福祉・社会系」の分野を選択して回答する形式になっており、「福祉系」で受験する場合は、「福祉系」の問題に対応できるよう準備しておく必要があります。また、3部では「福祉系科目」のみならず、「心理学」や「社会学」などの科目から選択して回答することも可能ですので、得意科目を「人間科学」の科目を横断して広く知識を身につけておくと、試験本番での応用が利くかもしれません。
参考:人事院ホームページ「国家公務員試験採用情報ナビ:試験情報」
http://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/mondairei/mondairei_13.htm
「厚生労働省」で働く「人間科学区分(福祉職)」の仕事内容
「厚生労働省」では「国家公務員総合職」の「人間科学区分」で採用された場合も、あくまで「総合職」として扱われますが、最初の配属先に特色があります。「厚生労働省」での「人間科学区分採用者」の最初の配属先は、厚生労働省内の「職業安定局」や「人材開発統括官の各課室」が一般的です。
その後も「人間科学分野」の専門性を活かしながら「総合職」として、雇用や福祉分野での政策の企画立案やその調整、管轄するハローワークなどの施設への指導や運営支援業務を担当するのが基本的なキャリアコースだと言われています。
中には「国際行政官」として「国際労働機関(ILO)」に出向する職員や、独立行政法人の研究員となる職員、都道府県の労働局で現場経験を積む職員、内閣官房で省庁横断チームの一員として活躍する厚生労働省の「人間科学職職員」もいます。
「厚生労働省」の「福祉系公務員」は、大枠では「総合職」ではありますが、「福祉」の専門知識を活かしながら、国と地域や、日本と諸外国の健康・労働の問題解決、政策立案などで活躍しています。
参考:厚生労働省ホームページ「採用パンフレット:厚生労働省採用案内 ~≪人間科学職≫を目指す方々へ~」
https://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kokka1/shinri04.html
「法務省」で働く「人間科学区分(福祉職)」の仕事内容
「法務省」では「国家公務員総合職」の「人間科学区分」で採用された場合に、「矯正局」もしくは「保護局」に採用されます。特に「福祉分野」で採用された職員は、「保護局」で活躍することが多く、「矯正局」では「心理学分野」での採用が主なようです。
「法務省」に採用された場合「矯正局」や「保護局」の職員として企画立案業務に携わる本省勤務になる場合や、「矯正局」の場合は全国の「少年鑑別所」や「少年院」、「保護局」の場合は全国の「地方更生保護委員会」や「保護観察所」などで勤務する場合があります。
「保護局」の仕事では「福祉」の知識や心理学、教育学、社会学等の人間科学の諸分野に関する専門的知識を活かして、「地方更生保護委員会」や「保護観察所」に在籍する「保護観察官」として、犯罪者や非行少年に対する保護観察、生活環境の調整、仮釈放などの審理のための事前調査などに従事するようです。
参考:法務省ホームページ「採用パンフレット」
http://www.moj.go.jp/jinji/shomu/kanbou_jinji03g.html
「警察庁」で働く「人間科学区分」の仕事内容
「警察庁」にも「国家公務員総合職」の「人間科学区分」での採用がある場合がありますが、「心理学分野」での採用が主のようです。「警察庁」のでは、「心理学」の知識を犯罪捜査に活かせるよう、「科学警察研究所」で「人間科学区分」での採用を行なっているようです。
参考:科学警察研究所ホームページ「採用情報:募集要項」
https://www.npa.go.jp/nrips/jp/recruit/guideline.html
「文部科学省」で働く「人間科学区分」の仕事内容
「文部科学省」にも「国家公務員総合職」の「人間科学区分」での採用が予定されていますが、「人間科学区分」として採用されている方の多くは「教育系科目専攻」のようです。
「文部科学省」に「国家公務員総合職」の「人間科学区分」で採用された場合も、「総合職」という扱いにはなるので、「教育」「科学技術・学術」「文化」「スポーツ」といったあらゆる分野のジェネラリストとして多様な部署への配属が考えられます。
「福祉」の専門知識を活かすという面では他の省庁を希望する方が良いかもしれませんが、「福祉」に加えて「教育」などにも興味があるという方は、やりがいのある仕事を見つけられる可能性があると言えるでしょう。
参考:文部科学省ホームページ「採用案内」
http://www.mext.go.jp/booklet/1294825.htm
【国家公務員専門職】「家庭裁判所調査官補」の仕事内容
「国家公務員」の「裁判所職員総合職試験」には、「家庭裁判所調査官補」の採用試験もあり、専門試験で「福祉系科目」を選択することができます。
「家庭裁判所調査官補」は全国の家庭裁判所で勤務し、数年経験を積むと「調査官」になるための昇級試験を受けることができます。「家庭裁判所調査官」は「家裁調査官」とも呼ばれ、家庭に関する争いや、非行した少年の処分の決定に関する業務を行うため、「福祉」の知識や専門的な視点が活かされる職業の一つと言えます。
【国家公務員専門職】「法務省専門職員」の仕事内容
「国家公務員」の「法務省専門職員」は、「国家公務員総合職」とは別に実施される「法務省」に専任の職員を採用する試験です。
「法務省専門職員」には「法務技官(心理)」「法務教官」「保護観察官」という職種があり、その中でも「法務教官」と「保護観察官」は「福祉」の知識や知見が活かされる仕事です。
「法務教官」と「保護観察官」を志望する場合には、採用試験で「福祉系科目」の問題を必須で回答しなくてはならないので、大学等で「福祉系科目」を専攻していた人が比較的目指しやすい職種と言えます。
【まとめ】国家公務員で福祉に関わるなら「人間科学職」
「国家公務員」には「福祉職」という区分はありませんが、心理学や教育学、社会学と「福祉分野」を合わせた「人間科学区分」という採用枠があることをご紹介しました。
「国家公務員」に求められるのは、高度な知識や専門性と共に、ジェネラリストとして広い、横断的な知識でもあります。「福祉」のみを学んできた方にとって、「人間科学職」として活躍していくのは大変な面もあるかもしれませんが、「国家公務員」として採用されると、「福祉」の知識を元にして、様々な専門性をもった職員と共に、国のあらゆる問題解決をする立場で仕事をする機会が得られるかもしれません。
また「福祉」だけでなく「教育」「心理」「社会」の分野も学んできたという方や、興味があるという方は、「国家公務員」の「人間科学職(福祉職)」を目指すことをおすすめしたいと思います。
まとめ
このページでは「国家公務員」と「地方公務員」の「福祉系公務員」について特集しました。公務員の「福祉職」として採用されると、様々な勤務先や業務内容があります。公務員ですので異動はつきものですが、どの職場でも身体面、精神面など、社会生活を送る上で困難を抱える人々に寄り添い、支えていくということは共通しています。
様々な面で総合的に福祉に関わることができる「福祉職」は、国の機関やどの自治体にも必要不可欠な職種です。「福祉系公務員」は、「福祉のエキスパート」としてあらゆる立場で国民や地域住民の生活を支える、やりがいのある職種と言えます。
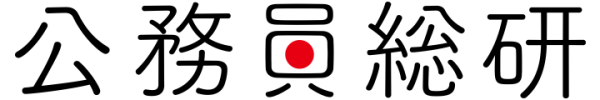




コメント