そもそも「みなし相続財産」とは?
相続は民法と密接に関係があるため、それを把握するには少し知識を入れておかなければ、話が分からなくなってしまいます。また、難しい用語も出てくるため、都度、理解しておかなければ、解釈を間違ってしまう恐れも否定できません。
そこで、少し本題に入っていく前に、今回のテーマを理解するうえで知っておいてほしい「みなし相続財産」について解説します。
「みなし相続財産」を一言で説明するのであれば、被相続人が亡くなった日には「財産」として所持していなかったにもかかわらず、相続人の財産となるもの、ということになります。
一般的によく思いつく相続財産は、「土地・建物」「預貯金」「株券」など、「すでに被相続人が所持しているもの」を相続人で分ける、というモノです。しかし実際には、それ以外のものもある、ということになります。
この「それ以外のもの」に当たるのが、「みなし相続財産」というわけです。
では、この「みなし相続財産に当たるもの」には、どういったものがあるのでしょうか?
「みなし相続財産」の扱いとなるものとは?
ではここで問題になってくるのが、「みなし相続財産」の扱いとなるものの種類です。一般的に、「みなし相続財産」という言葉すら聞きなれないものですから、わからなくても当然です。
・死亡保険金(死亡により、家族が受取人になっている保険金)
・死亡退職金
・年金(2か月分が口座へ入金されるので、亡くなってから受け取ることがあります)
・信託受益権
・債務の免除
・低額の譲り受け(いわゆる定額譲渡と言われるもの)
上記に挙げたすべてが、「相続人が受け取ることのない財産」ということになります。
みなし相続財産として、相続税の申告を行う可能性が誰でもあるわけですが、この「死亡退職金」については、公務員の方にとっては、知っておいてほしい内容なのです。
「死亡退職金」にまつわる判例
まず、死亡退職金の定義から説明しましょう。公務員の方であれば、すでにご存知かもしれませんが、あえて今後のためにご紹介します。
そもそもこれが何かといわれれば、公務員などの労働者が死亡した事を起因として支払われる退職金です。この場合、労働者であった被相続人の死亡により発生した、「財産請求権」という点に着目すれば、死亡退職金は相続における、みなし相続財産に該当すると解釈できそうです。
また、死亡退職金の法的性質は、性質上、賃金の後払いであること、残された 遺族の生活を保障するものとしての性質が非常に濃いものと考えられます。仮に、賃金の後払いという解釈をすると、更にみなし相続財産の可能性が高いということができます。
しかし実際は、死亡退職金の支給規定はそれぞれで決められるという性質があります。これが公務員における「死亡退職金」の基本的な定義になります。
実は、公務員の「死亡退職金の扱い」が以外にも、違う場合があった、という判例が存在します。しかし、その判例自体が昭和50年代のものであるため、詳しい資料がありませんでした。
しかし、内容を解釈すると、裁判所としての見解は、おおよそ以下の通りになるということが分かりました。
国家公務員退職手当法2条によると,「遺族」に死亡退職手当を支給するものと規定しており(同法2条1項),しかも,法定相続人の範囲・順位とは異なる人をその「遺族」として定められています。(同法2条の2)。
様は、法的には,国家公務員の死亡退職金の受給者は,法定相続人ではなく,「被相続人の収入で生活していたと考えられる人」であると定められているのです。
ともなると、死亡退職手当支給の法の本来の趣旨を尊重した場合、「法定相続人への分配」ということではなく,被相続人の収入で生活していた人の生活を保障をすること、を目的としているという解釈になります。
つまり、国家公務員の死亡退職金は,法令によって定められている受給者の固有財産ということであり,相続財産ではないとと考えられていることが分かります。
ということで、上記が「国家公務員」の場合です。では地方公務員の場合はどうなるのでしょうか。
では、被相続人が地方公務員の場合,地方自治法204条3項によると,この法律自体には、具体的な定めといえる法はなく,退職手当等については条例によって決めることができる、というカタチになっています。
ということは、被相続人が地方公務員である時には、勤務先である地方自治体の条例の定め方によって、死亡退職金が受給者の固有財産となるのか、それとも相続財産となるのかの解釈が、分かれてくるということになります。
しかし基本的には、地方公務員の退職金については,国家公務員法の例によることがすでに通達されているのが現状です。これは、昭和28年9月10日自丙行発45号(「職員の退職手当に関する準則・条例案」)と、国家公務員の場合と同様の取扱いがされているのが、一般的な解釈です。
つまり、国家公務員の場合と同じように、受給者の固有財産であるということ、また、それと同時に相続財産ではないということができます。
これを、国税庁のHPではどのように解釈しているのかといえば、質疑応答形式でしたが、以下の通りになります。
(国税庁HP「http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/03/09.htm」抜粋)
【照会要旨】
相続税法第3条第1項第2号の規定は、「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合」と規定していますが、死亡退職金の課税時期は、死亡退職金の支給が確定した時か、それとも当該死亡退職金の支払いがあった時のいずれですか。
【回答要旨】
死亡退職金の支給の確定があれば、死亡退職金の支払請求権(債権)という財産を取得したことになりますから、その時点において相続税の課税原因が発生しているというべきです。相続税法第3条の規定は、相続財産とみなされる財産を擬制しているに過ぎず、課税時期については、定めていないと解されます。
したがって、死亡退職金については、死亡後3年以内にその支給が確定すれば、実際の支払いが3年以内であるかどうかを問わず相続税が課税されることになります。
と、上記のような質疑解答例が照会されていました。つまり、この解釈の仕方を変えるのであれば、被相続人が亡くなってすぐに請求した「死亡退職金」については、相続税の課税の対象とはならない、ということができます。ただし3年を経過すれば、それは相続税の対象となる「財産」ということになります。
しかし、これを読むと「あること」に気付きます。そうです。「3年以内に支払いが行われなかった場合」ということです。そういった場合が実際に存在するのでしょうか。いったいどのような場合に、そういった事態になってしまうのでしょうか。
3年内に確定が行われていない「死亡退職金」とは
ここで、注意が必要なのは、「支払いが行われていない場合」の解釈です。これは少し語弊があるかもしれませんが、実際に「支給があった」という事実ではなく、「支給するということが確定した」ということなのです。つまり、支給が確定している「死亡退職金」であれば、相続財産の対象にはならないということができます。
少しややこしくなってきましたよね。ではもう少し、ご説明します。
確定しているというのは、実際に支払ったという事実ではなくてよいというのは、前述しました。では、何が決定している必要があるのかといえば、それは「金額」です。この場合の「確定している」という要件は、言い換えれば、金額が「確定している」ということになります。つまりこの「金額の確定」がされていれば、実際の支払いが3年経過後であったとしても、相続財産にはならないということができるのです。
例えば、あまりいい例ではないかもしれませんが、死亡退職金をめぐる裁判を起こしたとします。裁判に時間がかかり、実際に被相続人がなくなってから2年以上経過し、それでもまだ3年は経過していないという時に、死亡退職金の支払いが決定し、金額も決定したとします。そうすると、3年以内に金額が確定しているので、4年後にその支払があったとしても相続財産の対象にはならない、ということができるのです。
確かに、あまりいい例ではありませんがこういった「可能性」が全くない、というわけではありませんから、参考に予備知識程度に知っておくと、万が一の時に役立つかもしれません。
この他にもある、他人事ではない「みなし相続財産」
必ずしも、死亡退職金を受け取るという選択肢に至るとは限りません。
国税庁に紹介されている例は、以下の通りで、会社員を対象としたものになりますが、参考になるのでご紹介します。
(国税庁HP「http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/03/10.htm」参照)
A(株)は、社長が死亡したため、株主総会及び取締役会の決議に基づき死亡退職金として1億円をその遺族に支払っていましたが、その後、遺族から退職金受領を辞退したい旨の申し入れがあり、1億円が返還されました。この場合、相続税の課税はどのようになるのでしょうか。
【回答要旨】
社長の遺族が受領した退職金1億円は、その支給について正当な権限を有する株主総会及び取締役会の決議に基づいて支給されたものであることから、受領した退職金を返還したとしても相続税が課税されることにかわりはありません。
ただし、返還理由がその退職金の支給決議が無効又は取り消し得べきものであった場合において、その無効が確認され又は取り消しがなされたことが、権限を有する機関の議事録等から明らかであれば、相続税の課税対象とはなりません。
上記の例は株式会社が例となっているので、公務員のように「議事録等から明らかであれば」という、この証拠書類を収集できれば、同じような判断ができるといえます。ただ、今回の例は「議事録」なのかといえば、亡くなって辞退している遺族は、社長の親族と考えられるからです。一般企業の場合は、必ず役員についてのことは「議事録」を作成しますから、そこが公務員とは少し異なる部分かもしれません。
死亡退職金が支給される場合は、役員だけとは決まっていませんから、同じような状況になりそうな場合は、証拠勝利を集める必要があります。「辞退している」「もらっていない」「受け取っていない」ということを証明できる書類です。
この他にもある、「みなし相続財産」とは
多くの人が該当すると考えられる「みなし相続財産」が実はあります。それは死亡保険金です。死亡保険金は、当然、亡くなった本人が受け取ることはありません。つまり、先にも述べた解釈をするのであれば、「亡くなった後に、火h権者が受け取る財産」ということになります。
しかしこの死亡保険金、実は掛け方や受け取る人によって、その解釈が変わるのです。
まずは、以下のような場合を想定しましょう。ケースは3つです。
被保険者 保険料の負担者 保険金受取人 税金の種類
A B B 所得税
A A B 相続税
A B C 贈与税
このように3パターンのかけ方があったとします。どれも、現実に認められている生命保険の掛金の掛け方の方法です。
その場合においても、被相続人に当たるのはAさんです。
所得税の課税が表記されているものは、「AさんのためにBさんが、Bさん自身を受取人として生命保険に加入した場合」です。
そして2番目の相続税の対象となるものは、「AさんがBさんを受取人として、Aさん自身が保険料を納めた場合」です。
最後に3つ目は、「Aさんの保険料をBさんがふたんして、新たな受取人Cさんに保険金を渡す場合」です。
こう聞くと、少しわかりにくいかもしれ間sねなg、この3つのケースは、五組じかに存在するケースなのです。
例えば2番目は、ご主人が奥さんのために、自分が病気になった後困らないように、とご主人が奥さんを受取人として保険をかけているケースです。普通にあるパターンといえます。これが相続税の対象となるのです。
では1番目と3番目はどういったケースなのか。1番目は、ご主人がなくなったら自分が困るので、自分が困らないようにするために奥さんが掛け金を負担し、自分が保険金を受け取る、といったものです。「自分が払って自分に変える」というこのケースは、所得税の対象です。「予期せぬお金が入ってきた」となる場合は、相続税の対象ですが、掛けている人と受取人が同一であれば、予期せぬお金とは言い難いものがあります。
3番目は、奥さんがご主人の保険金を支払っているが、その保険金の受取は自分の子どもにしている、といったケースです。これも十分身近にあり得るケースです。子どもの将来のために少しでもお金を残しましょう、といたところでしょうか。
贈与税の対象ではありますが、実際に実務上では相続税を納めるに至らないケースが多いのも事実です。
それは、負ってご紹介するとしましょう。
このように、2番目のケースが相続税の対象となり、みなし相続財産として判断されるものになるのです。
ただ実際は、保険金の受取人は生前より決めているので、みなし相続財産ではありますが、相続税対策として活用することもできます。
気になる、遺族年金の扱いは?
遺族年金お扱いは、果たしてどうなるのでしょうか?
これもく税調のHPでしっかりと説明しているのですが、一番わかりやすい部分のみ抜粋します。
(国税庁HP「http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4123.htm」より一部抜粋)
厚生年金や国民年金などを受給していた人が死亡したときに遺族の方に対して支給される遺族年金は、原則として所得税も相続税も課税されません。また、死亡したときに支給されていなかった年金を遺族の方が請求し支給を受けた場合は、その遺族の方の一時所得となり、相続税はかかりません。
ここで知っていていただきたいのは、税金の流れについてです。どのような流れで課税されていくのか、それを知っておくと、この文章も、もう少しわかりやすくなるかもしれません。
相続税の課税の対象となった場合、所得税は課税の対象外となるのが基本ルールです。また逆に、相続税は課税されていないという場合は、所得税が課税されるというような、一定の流れがあります。
そしてさらに、日本の個人へ課税される税院の場合は、「担税力」と「社会的通念上」という考え方もベースにあります。
担税力とは、税金を納めるだけの金銭的な体力といえば、わかりやすいかもしれません。所得が多ければ、それだけ、税金を納める能力もある、という事になります。
また、「社会的通念上」とは、一般常識に照らし合わせて見てどうか、という判断になります。あまりにも一般常識tかけ離れている解釈は行いません。
つまり上記のような遺族年金であれば、残された家族がその後も生きていけるように配慮されたお金ということができます。
ただし、亡くなった方の年金を請求して受け取る場合と、遺族年金として受け取る場合とでは、若干の差がありますので、その点においては十分注意しておく必要があります。
なぜ「相続税」がスポットを浴びているのか
もともと、国税庁や税務署は、本来得られなかった税収を「相続税」から、何とか徴収できないか、という動きがありました。このような表現は適切ではないかもしれませんが、知識人が多い法人をターゲットに調査するよりも、知識が少ない個人をターゲットとする方が、調査をした際の追徴を期待できる、と踏んでいた側面があるようです。
実際に、相続税を納めるようなケースは、専門家にその申告の依頼をしていることがほとんどなので、なかなか思惑通りにはいかないのが現実ですが、そういった意味で「相続」にターゲットが絞られていた、というのは否定できません。
また、税制改正により、相続税の基礎控除額も減少し、今まではいわゆる「お金持ち」が対象だった相続税も、一会社員の家庭でも、相続税の申告が必要になってしまうケースが出てきました。それだけ、国から見れば、「相続」は税金を徴収するのに格好の「エサ」だったのでしょう。
相続財産とは、気付かない部分にもあるかもしれません
「みなし相続財産」というものが存在するように、必ずしも被相続人が知っている、もしくは把握している財産のみとは限らないということを、知っていただけたのではないでしょうか。
相続財産がこれしかない、と、すべてを把握したつもりでいても、実際は違うということがあり得るのが相続です。
相続財産がすでに多くあるという人は、相続対策として生前贈与というものを検討されてみてもいいでしょう。相続を円滑に行うためには、いかに財産を把握できているかがポイントです。
また、この「相続財産を正確に把握していない」ということがどういった事態を招く可能性があるかについて触れておきます。
相続税そのものは、基礎控除と言われるものがあるので、その控除の範囲内であれば申告をする必要がありません。つまり、相続税としての税額がないので、わざわざ申告をしなくてもいい、ということになります。(一部例外もあります)
もともと、本当に財産がない、という場合か、基礎控除が受けられる人数、つまり相続人が多い場合は、心配する必要がないかもしれませんが、計算を行った際に、「ギリギリ申告が必要ない」となった場合、これは「みなし相続財産」のような、被相続人が知らない、亡くなった後から出てくるような財産があった場合には、相続税がかかる可能性があり、その場合には申告が必要となります。
基本的に、相続税の課税となる場合は、その他の税額控除を利用できる可能性もありますので、そのあたりも検討していかなければなりません。
このように、相続財産がしっかりと把握できているかによって、その後に必要となってくる手続きや、また段取りも変わっています。どのような財産があるのか、把握できていないことにより、事前遺体策ができなかったということが一番もったいないケースです。そういったもったいないことをしないように日頃から
・何がどこにあるかを記した記録を残しておく
・遺言書を作成しておく(できれば公証役場にて作成の方がよい)
これらが最低限わかるようにしておけば、万が一の時が起こっても、対応しやすいでしょう。
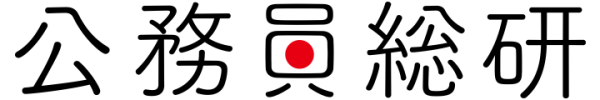









コメント