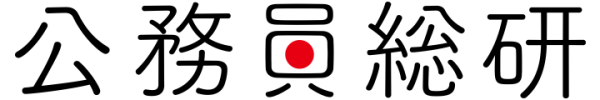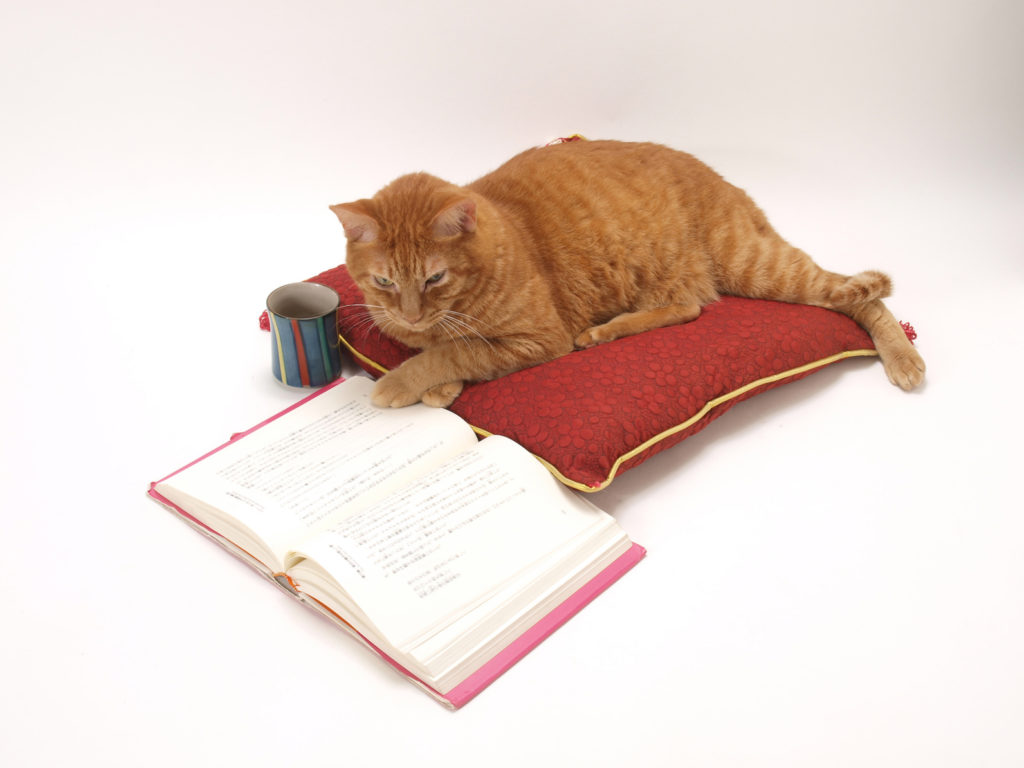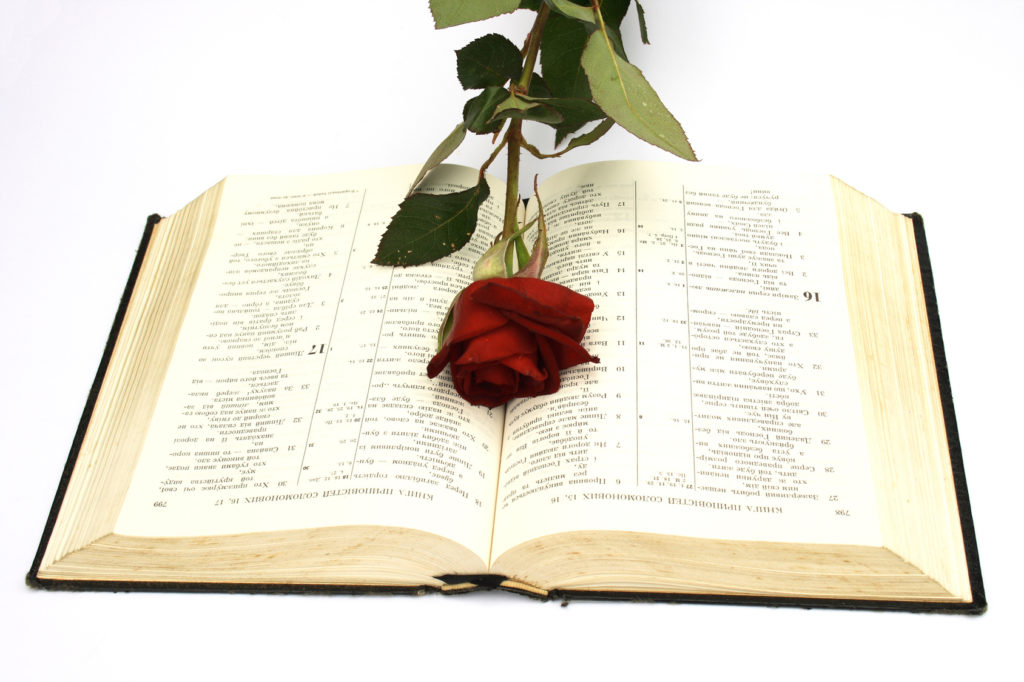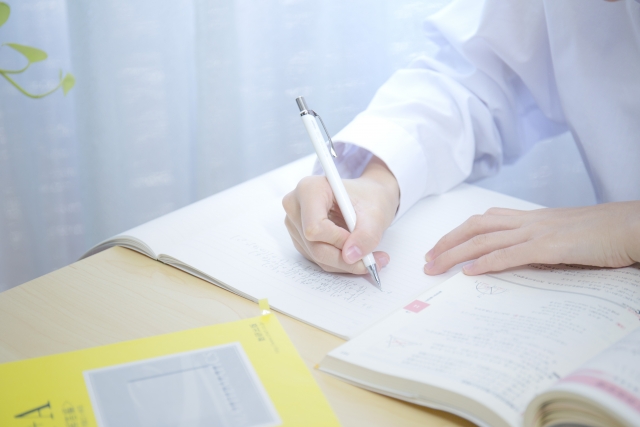歴史– tag –
国家公務員採用試験や地方公務員採用試験の教養試験科目「歴史」をテーマにした記事の一覧です。
-

安倍晴明は式神を使わない?実は「国家公務員」だった陰陽師
式神は召喚しない? 国家公務員である「陰陽師」の本当の働き 陰陽師といえば、野村萬斎さんが「安倍晴明」を演じた映画『陰陽師』を思い出す方も多いのではないでしょうか? 本作では、この世とあの世が繋がり、魔物たちが存在していた平安時代に、式神を... -

【老朽化から管理、再整備まで】日本のインフラを巡る問題点を再考
インフラの概要と種類について インフラとは社会基盤のこと 当たり前に耳にするようになった「インフラ」という言葉は英語の“infrastructure”(インフラストラクチャー)から来ていて、元々は「基盤」や「下層構造」などの意味があります。日本では、「社... -

稲作と戦争が本格的に始まった弥生時代、邪馬台国はどこにあったのか?
弥生時代の特徴 稲作の普及 1万2000年以上の長きに渡る「縄文時代」とその後の「弥生時代」には厳密な境目が存在しません。 一般的には弥生時代のスタートは、「稲作が始まった時期」とされ、紀元前4世紀ごろと考えられてきました。しかし縄文時代晩期には... -

およそ1万2000年間に及ぶ「縄文時代」のミステリー
縄文時代以前の旧石器時代は日本に存在したのか? 旧石器時代の時期 現生人類(ホモ・サピエンス・サピエンス)の祖先であるホモ・サピエンスが登場するのが今からおよそ180万年前です。さらに、アフリカの地で現生人類が誕生するのが25万年前とされていま... -

【映画で世界史を学ぶ(1)】歴史映画「ダンケルク」
「歴史映画で世界史を学ぶ」シリーズ第一回は、映画「ダンケルク」です。昨年公開の映画で、今年のアカデミー賞作品賞・監督賞にノミネートされました。 『インセプション』、『バットマン・ダークナイト』、『インターステラ』など、複雑で難解な映像表現... -

江戸時代、寛政の改革と天保の改革の合間にあった化政文化の学問分野
化政文化の学問分野の柱「朱子学」 寛政の改革と朱子学 江戸時代を代表する学問といえば「儒学」になります。儒学とは中国の孔子の教えであり、6世紀に朝鮮半島を経て日本に伝来しました。江戸幕府はこの儒学を公認の学問に選んだのです。なぜ江戸幕府は儒... -

江戸時代、寛政の改革と天保の改革の合間にあった化政文化の芸能分野
化政文化の背景 寛政の改革の反動 田沼意次が老中首座だった頃に幕府の財政は立ち直りの兆しを見せましたが、天明の大飢饉や浅間山の大噴火、農村の荒廃などによって再び苦しい状況に陥ります。一揆や打ち壊しが相次ぎ、田沼意次は失脚。幕府は松平定信の... -

試験問題「日本の文学」シリーズ!第一回:「日本古典文学」
今回解説する日本古典文学は、奈良時代から鎌倉時代に誕生した以下の作品です。 ▼歴史書 奈良時代の歴史書「古事記」「日本書紀」 ▼和歌集 奈良時代の和歌集「万葉集」 平安時代の和歌集「古今和歌集」 鎌倉時代の和歌集新古今和歌集」 ▼物語 平安時代の物... -

近代の日本における「憲法制定」と「議会開設」までの道のり
1868年に江戸幕府は廃止され、新政府が誕生します。王政復古により日本の舵取りを任されたのが「明治政府」です。この新政府の基本方針は「五箇条の御誓文」として表明されています。 明治維新において、日本の仕組みは大きく変わることになりました。列強... -

江戸時代、上方の町人が中心となって盛り上がった元禄文化とは
元禄文化の背景 元禄文化の時期の将軍は誰なのか 「江戸時代」とは徳川家を将軍として265年間もの長きに渡り続いた最後の武家政権です。戦国時代は終焉し、戦乱による被害は大きく減ったものの、災害や飢饉などによって庶民の苦しみは継続していました。 ... -

江戸時代、享保の改革と寛政の改革の合間にあった宝暦・天明文化とは
宝暦・天明の文化の背景 前後にある改革とは 江戸時代を区分していくと、幕府に財政的に余裕ができた時期と、財政が厳しく引き締めが行われる時期が交互に存在していくことに気が付きます。財政難に陥ると幕府は改革を行いますが、それが江戸時代の中で有... -

日本オリジナルの文化が花開く国風文化・院政期の文化とは
国風文化の特徴(文学作品) 仮名文字の文学の流行 「国風文化」は、日本独自の文化が大きく花開いた10世紀から11世紀の平安時代最盛期にあたります。華やかな貴族文化の象徴ともいえる時期です。 これまでの文化と大きく異なるのは「女性の感性」が強く反... -

京都への遷都、新興仏教の台頭、そして漢詩ブームの弘仁・貞観文化とは
新興仏教「密教」の台頭 平安京への遷都は何のために行われたのか 奈良を中心に、仏教文化として飛鳥・白鳳・天平文化が花を開かせることになりましたが、一方で朝廷や政治に僧侶が強く干渉するようにもなっていきました。 764年の藤原仲麻呂の乱の後に権... -

奈良を中心にして花開いた仏教文化、飛鳥・白鳳・天平文化とは
仏教文化 仏教の伝来と興隆 中国大陸から朝鮮半島を経て、日本に様々な新しい文化が伝来します。その中で日本に大きな改革をもたらすことになったのが新興宗教の「仏教」です。 現代でこそ日本にしっかり根付いている仏教ですが、6世紀後半から7世紀にかけ... -

謎に包まれた4世紀を含め、およそ400年続いた古墳文化とは
縄文時代、弥生時代に続くのが「古墳時代」になります。年代的には3世紀の半ばから7世紀にかけてのおよそ400年を古墳時代と呼びますが、詳細が記されておらず、わからないことも多くあります。 古墳というのは大王や豪族といった権力者の墓です。「前方後... -

公家文化と武家文化の融合・室町文化(北山文化・東山文化)
日本の歴史を紐解いていくと、その時代の特徴を背景にした文化が誕生し発展していることを知ることができます。古くは天平文化や国風文化、江戸時代の元禄文化や化政文化などに分けられます。 室町幕府が存在していた1336年から1573年にかけて公家や武家を... -

武士の気風を反映した新しい文化の誕生・鎌倉時代の文化・仏教・経済
鎌倉時代といえば、本格的な武家政権「鎌倉幕府」が誕生した時代です。征夷大将軍となった源頼朝は関東に幕府を開きました。これまでは京都が政治の中心でしたが、源頼朝はそれを大きく変えたのです。 またこの鎌倉時代を象徴する出来事としては、新しい仏... -

新興勢力の台頭による豪華で壮大な「安土・桃山文化」
鎌倉文化、室町文化(北山文化・東山文化)に続くのが、「安土・桃山文化」になります。単に「桃山文化」と呼ぶこともあります。時期的には、「織田信長」「豊臣秀吉」が台頭し、天下統一に向けて激動の時代となる16世紀後半から17世紀の始めです。 実に短... -

日本の高度経済成長とは?終戦10年待たずおきた「東洋の奇跡」について
「東洋の奇跡」といわれた日本の「高度経済成長」について 1945年(昭和20年)8月15日に日本はポツダム宣言を受諾し、アメリカ・イギリス・ソビエト連邦・中華人民共和国といった連合国に降伏します。第二次世界大戦の終結です。 日本は国力のすべてをつぎ... -

【頻出歴史問題】第二次世界大戦の勃発と拡大、各国の動きと思惑(後編)
前回お伝えしましたように、ドイツのポーランドへの侵攻から端を発した侵略戦争は瞬く間に世界に広がっていきます。第二次世界大戦の勃発です。枢軸国のドイツ・イタリア・日本は手を結び、それぞれが目標とする領地獲得に動き出すのです。対する連合国は... -

【頻出歴史問題】第二次世界大戦の勃発と拡大、各国の動きと思惑(前編)
日本が満州事変から引き続き日中戦争を始めた頃、ヨーロッパでも第一次世界大戦で敗北したドイツが危険な動きを見せ始めていました。ドイツがまたもや世界大戦勃発の火種となるのです。 第一次世界大戦と大きく異なる点は、第二次世界大戦には日本も積極的... -

【頻出歴史問題】政党政治の終焉とファシズムの台頭-昭和時代の日本
「昭和時代」は1926年12月から1989年1月までの期間になります。20世紀のほとんどといえるでしょう。この期間に日本は第二次世界大戦の敗戦という経験をすることになります。未曽有の犠牲者が出た、まさに悲しい歴史です。1945年の終戦を区切りとして昭和時... -

【頻出歴史問題】大正時代における民主主義の発展と日本の近代化について
1912年7月20日から1926年12月25日までという短い期間ながら、政党勢力が進出し、これまでの藩閥政治に取って代わる大事な機会となった「大正時代」。この時期は、世界が第一次世界大戦という混迷の中にあった時代でもありました。 第一次世界大戦について... -

【頻出歴史問題】「日露戦争」と「ポーツマス条約」と列強諸国の思惑
日本の近代化にとって重要な機会となった「日清戦争」と「日露戦争」。日清戦争のわずか10年後に日露戦争は勃発します。「得をしようと(1904年)日露戦争」「遠くで行う(1905年)ポーツマス条約」といった年号の語呂合わせもありますね。日露戦争とポー... -

【頻出歴史問題】人類最初の世界大戦「第一次世界大戦」とヴェルサイユ条約
第二次世界大戦は日本が積極的に戦ったことから有名な戦いや出来事が多くありますが、第一次世界大戦の主戦場がヨーロッパであったことと、日本はほとんどこの戦いに参加していないため、歴史の授業でも覚えることは少な目になっています。 この時期の代表... -

【頻出歴史問題】戦国大名・織豊政権とは?下克上の時代へ
歴史が好きな方に「何時代が好きですか?」と尋ねると、「戦国時代」や「安土・桃山時代」と答えられるケースが多いですね。もちろん、そんな殺伐とした時代の何が楽しいの?と感じられる方もいるでしょう。この時代は小説や映画、大河ドラマやゲームなど... -

【頻出歴史問題】日清戦争とは?日本の近代化と帝国主義
明治維新後、日本は近代化を加速させ、軍備も拡張、諸外国と戦争を行うようになります。その最初が「日清戦争」です。「人は苦しい(1894年)日清戦争」といった年号の語呂合わせもあります。19世紀も後半、いよいよ20世紀という時期から日本は列強諸国の... -

【頻出歴史問題】室町幕府とは?鎌倉幕府の滅亡から建武の新政、新幕府まで
公務員採用試験の頻出歴史問題「室町幕府」についての解説ページです。鎌倉幕府に次ぐ武家政権の「室町幕府」。足利尊氏や足利義満、勘合貿易や鹿苑寺の金閣などは有名ですが、その誕生の背景はあまり知られてはいません。今回は鎌倉幕府の滅亡、建武の新... -

【頻出歴史問題】公家から武士へ、平家政権と摂関政治・院政について
公務員採用試験の頻出歴史問題「平家政権」についての解説ページです。「いい胸毛(1167年)の平清盛、太政大臣に就任」なんていう年号の語呂合わせが有名ですね。対照的に摂関政治→院政→平家政権の政治の流れは実に複雑です。様々な勢力が登場しての政争... -

【江戸の3大改革】「天保の改革」が目指したものは何か?経済安定化への道
公務員試験の歴史分野で頻出問題となる江戸時代の幕府政策3大改革解説シリーズ。今回は、江戸の三大改革の最後の改革「天保の改革」についてです。江戸幕府、第12代将軍・徳川家慶の治世で、寛政の改革からおよそ40年後のことで、改革の内容にも似ている...
12