一般的な生活発表会とは?
一般的に生活発表会とは、子どもたちが日々の保育で経験したことや努力したことを保護者に披露する、貴重な機会です。この会を通じて、子どもたちは達成感や緊張感、観てもらえる嬉しさを味わうことができます。
生活発表会は、各学年の発達に合わせた内容で行われることが多いですが、年長組においてはどの幼稚園でも劇をすることが多いです。
今回はその年長児が『劇』について、ねらいや段取り、大事なポイントについて紹介します。
『劇』をするねらいは?
具体的に私が勤務していた公立幼稚園年長組の生活発表会『劇』では、どのようなねらいをたてていたのか紹介します。
年長組は子どもが主体となり、グループ活動で進めていくことができるようになる学年です。
よって、大きく2つのねらいをたてていました。
1)グループの中で自分の考えを友達に伝えていけるようにする。
2)色々な感情体験をしながら、友達と一緒に作り上げた満足感や充実感を味わう。
『劇』の活動に入る前に教師がしておくこと「グループ編成」
劇の活動を始める前に教師が最初に行うことは、劇のグループ編成です。
グループ人数の目安
1グループの人数が多すぎると、グループ活動の話し合いが進めにくく、子ども1人ひとりの力が発揮される場面が少なくなってしまいます。
そのため、私が受け持っていたクラスは30人少しのクラスでしたが、まずグループを3つに分けました。
だいたい10人程度になることを目安としていました。
グループ編成で大事なこと
グループ編成するにあたって大事なことは、教師が各グループの力を均等に分けるのではなく、個々の実態から課題を思い浮かべ、1人ひとりの課題が達成できるようなグループを考えることです。
グループ編成の例
例えば、子どもの実態が『普段自分の考えを言える子』であれば、『友達の思いを受け入れたり、調整する力が育ってほしい』という願いを子どもに対して持つと思います。
その場合、教師は同じような課題を持つ子ども達を1つのグループに集め、グループ活動の際に互いの意見がぶつかる場をあえて作ります。
そして、子どもが『自分の意見だけ通していては相談が成立しないこと』に気づく経験をできるようにしていきます。
逆に、子どもの実態が『普段あまり自分から前に出ていかない子』であれば『自分の思いを出せるようになってほしい』という願いを子どもに対して持つと思います。
その場合、教師は同じような課題を持つ子ども達を1つのグループに集め、グループ活動の際に、自分の考えを友達に伝えていかないと話を進めたり物事を決めていくことができない場をあえて作ります。
そして、子どもが『自分の考えを周囲に伝えていく大切さ』に気づく経験をできるようにしていきます。
劇をする上での段取りと大事なポイント
では実際に生活発表会に向けて保育の中で『劇』をしていくにあたり、どのような段取りで進め、大事なポイントは何であるのかについて、5つご紹介していきます。
劇をする上での段取りと大事なポイントその1:グループごとに何の劇をするか決める
最初に、教師がねらいをもって分けたグループごとに集まり、何の劇をしたいのか子ども達で相談して決めます。
教師が3冊ほど絵本を提示し、子ども達に読み聞かせた上で、どの絵本を劇にしてやってみたいか個々に考えを聞いていきます。
子ども達から『どうしてその絵本が良いと思ったのか』等を聞き、グループの中で友達の考えを聞きながら1つの劇に決めていきます。
教師が援助するポイントは、グループ編成の際に考えた“ねらい”を達成できるように意識しながら子ども達に関わることです。
劇をする上での段取りと大事なポイントその2:セリフや動きの練習を進める
次に発表会に向けた活動内容として行うことはセリフや動きの練習です。
練習に入った段階では、セリフや動きも教師と子どもたちで相談しながら進めます。
セリフに関して教師が援助するポイントは、劇の流れに合っている言葉であれば、子ども自身から出てきた言葉を『セリフ』として取り入れるようにすることです。
教師が一方的に教え込んだセリフは、実際子どもが言いにくいものであることがあります。
子ども達自身からでてきた言葉をセリフとして使っていくことで、子どもたちが劇を進めていきやすいように整理してあげることが教師の役割です。
また、動きに関して教師が援助するポイントは、自分の出番が終わったら、座って待っているだけではなく、自分達で道具の出し入れをしたり、音響を操作したり、必要な役割があることにも気づけるよう助言をすることです。
子ども達が主体的に進めていけるように、教師がサポートしていく側にまわることを常に意識することが大事です。
劇をする上での段取りと大事なポイントその3:衣装やお面、道具作りをする
セリフや動きの練習が進んできたら、次に進めていくことは衣装やお面作りです。
衣装やお面があることで子ども達も役になりきりやすく、道具があることで観客にも劇が分かりやすくなり、子ども達自身も動きやすくなります。
教師が援助するポイントは、衣装やお面、道具も子どもたちが自分達の手で作ることができるよう教材準備をすることです。
私は、衣装は子どもたちも切り貼りしやすいよう、カラーポリの素材を選び、子供が素材や技術の経験を広げられるよう型紙を用意していました。
年長になれば、子どもが自分で型紙を使ってマジックでラインを取り、はさみで切り、セロテープで貼り付けることも十分できます。はさみで切りにくいところがあれば、グループの仲間にビニールをおさえていてもらい、協力して作るという経験もできます。
すべて教師が作ったものを与えられるのではなく、必要な物は子ども達自身で作り進められるように、教師の教材準備、下準備が重要です。
劇をする上での段取りと大事なポイントその4:学級の中でグループ同士を見合う
発表会に向けた活動内容として、ある程度劇の流れが仕上がってきたら、グループごとに互いの劇を見合う場を設けていました。
子ども達は、劇を見てくれる人がいることで、自分の役割を果たしている姿を認められ自信に繋がります。
教師が援助するポイントは、見ている子どもたちに「個人」を見るのではなく、「グループ全体」を見るように指導することです。
表現していた子どもが、見ていた子ども達に「~ちゃんの声が聞こえなかった!」等と名指しで言われては自信をなくしてしまいます。
教師は、友達の良いところを自分たちのグループに取り入れることができるよう、「〇〇くんの〜がよかったね」と言葉をかけることがポイントです。
劇をする上での段取りと大事なポイントその5:発表会本番を経験する
子ども達はこれまでの練習の成果を生活発表会当日、保護者に見てもらいます。
教師の援助のポイントとしては、これまでの子ども達の頑張りの過程を十分に認め、達成感を感じられる言葉を丁寧にかけることです。
いよいよ発表会、その時に大事なこと
発表会当日の場で、保護者に当日の子どもの姿を見てもらうだけでは十分ではありません。
教師がこの発表会を通して、どんな思いを持って取り組んできたのか、教師が大事にしている点を伝えていくことが必要です。
具体的には、当日までの過程を写真や動画、掲示物等で知らせるようにしていました。
当日、もし子どもが普段の力を発揮できなかったとしても、それまでの取り組みを理解しておいてもらうことで、子ども達の成長の過程を保護者に分かってもらうことができるからです。
まとめ
今回は公立幼稚園の年長児生活発表会『劇』の体験談を紹介しました。
各園色々なやり方があると思いますので、1つの参考になれば嬉しいです。
大切なのは子ども主体で進められるようにすること、子どもが達成感を感じられるようにすること、個々を活かしながら友達と協力して取り組めるようなものにすることです。
教師にとっては頭を悩ませる行事の1つかと思います。しかし、『子どもたちと一緒に作り上げていく』ということを頭に置き、保護者にもその意図とねらいを明確に伝えていきながら、子ども達の発達にとって意味のある行事になるとよいですね。
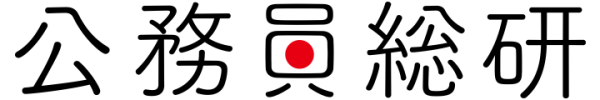









コメント